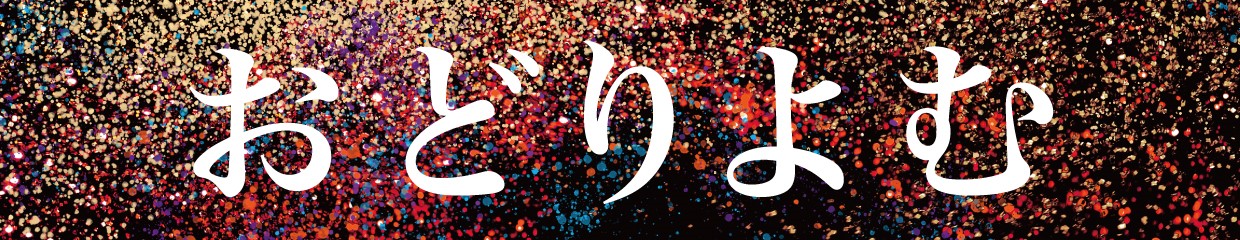重力という呪縛からの解放 — ナセラ・ベラザとのクリエーションから —

ナセラ・ベラザ『L'Envol』(© Laurent Philippe)
ナセラ・ベラザと出会ったのは、2013年のパリでした。
2013年に活動拠点をイスラエルからフランスに移し、自身の振付メソッドや創作スタイルを確立させるために試行錯誤を行っていた時期にナセラと出会うことができたのは、私の振付家人生において大きなターニングポイントになっています。私の創作に影響を与えたアーティストは?と聞かれたならば、山海塾とナセラの名前をあげるでしょう。
私は、2011年ごろ、スランプに陥っていました。それは所属していた舞踏カンパニー山海塾のメソッドや創作スタイルが身体、思考、美意識、哲学に至るまで染み込みすぎていたため、どうにかして、そこから抜け出すことに必死でした。そんな中、ナセラのプライベートオーディションに参加し、翌年にリヨン・ダンス・ビエンナーレで発表する『La Traversée(渡洋)』という作品にダンサーとして参加することになりました。この作品は、2014年9月に Dance New Air 2014(会場:青山円形劇場)でも上演されました。しかし、私はリヨン・ダンス・ビエンナーレ初演の2週間前にナセラが求めるクオリティまで作品を踊りこなすことができなかったため、メンバーから外れることになりました。これまでのダンス人生の中で初めての経験でした。
しかし、そのおかげとも言うべきか、膨大に書き留めたクリエーションノートをもとに、ナセラと山海塾のメソッドを2年に渡って比較研究することで「空気の風景」という独自のメソッドを確立しました。現在でも、私の創作の中心にあります。
私がナセラのクリエーションに参加したのは、2014年1月から6月、モロッコ・フランスを含む4カ国9都市でのアーティスト・イン・レジデンスでした。各都市、1週間から2週間程度の滞在制作を行い、ワーク・イン・プログレスの発表を繰り返しました。クリエーションの初期段階から作品の構想や振付は、ほぼ完成されていました。
『La Traversée(渡洋)』は、ジェームズ・タレルと安藤忠雄が手掛ける直島の家プロジェクト「南寺」を彷彿とさせる暗闇のシーンから始まります。漆黒の闇の中、ダンサーが走り回る気配に観客の意識は集中していきます。ゆっくり、照明と音楽のゲージを上げていくことで空間が膨張していきます。その間も4名のダンサーが数十分間、大きな円を描くように自転と公転の軌道を描き、ステージ上を滑るように走り続けるシンプルな振付ですが、緻密に計算された照明、音楽、振付、空間デザインによって瞑想的な宇宙空間をナセラは作り出していきます。
ナセラは、旋回運動やカリグラフィーと呼ばれる動きを繰り返す儀式的振付作品を数多く手掛けてきました。シンプルな動きを多角的に研究するため、世界各国の儀礼や祭儀をリサーチすることで普遍性というものを追及し続けているように感じます。
ナセラは、クリエーションの初日から様々な言葉をダンサーに投げかけることでイメージの共有を図っていきます。
例えば、稽古場でナセラが語りかける言葉には以下のようなものがあります。
「頭のてっぺんから、足のつま先までの意識を均等に保ち、一体化させなさい。」
「動きに始まりを作らないように、イメージに耳を澄ませ。イメージが訪れたらそれをただ受け入れなさい。」
「自分の身体を空間に広げなさい。」
「原因と結果が連なるように、抵抗せずに動き続けなさい。」
「イメージを身体の中に留めるのではなく、イメージが自分の身体を通り抜け、運ばれるように動いてみなさい。」
「恐れずに、もっと冒険しなさい。」
「考えることを諦めなさい。イメージに身体を委ねなさい。」
「始まりと終わりのない永遠に続く道を想像しなさい。」
「背中を意識して!もっと自分のドームを広げなさい。」
「音、照明、空間、パートナー、身体への意識を常に均等に意識し続けなさい。」
ナセラは、常に自分が目指す作品の終着点を明確に持っている振付家です。
だからこそ、それぞれ異なる身体性や文化背景を持ったダンサー達に対して、様々なイメージを投げかけることで共通言語を生み出そうと試みます。そして、ナセラはダンサーに客観性を求めます。個性や肉体といった個の存在を主張するのではなく、極限まで動きを追及することで身体を現象化させる高みへ連れていきたいと考えています。
ナセラの作品は、儀式的・ミニマル・抽象的・宇宙・瞑想などの言葉で説明されることが多くありますが、私はとても詩的な作品だと思っています。ナセラは、どの国に行っても道端で売られているDVDを購入したり、映画館によく通ったりしていました。リハーサルでナセラは、映画や文学の影響を多く受けていると話したことがありました。私も客席でナセラの作品を鑑賞した時、目前に広がる宇宙のような壮大な物語を見ているという感覚から、次第に「見る側と演じる側」がリンクすることで第四の壁が取り払われ、詩的な扉が開いていく錯覚に陥ったことがあります。
最後に私のダンスが何故、ナセラに受け入れられなかったのかを分析すると、ひとつに重力との関係性にあります。山海塾の舞踏では、「重力との対話」という哲学が徹底的にメソッドや振付に落とし込まれています。そのため、私の動きは、どうしても腰を少し落とした摺り足のような歩行や地に根を張るような重心によって、上半身を解放していく動きが特徴的でした。しかしナセラは私に「流れる」という言葉を稽古場で語り続けました。それは、重力という人間が逃れることのできない呪縛から、イメージを信じることで解放されてほしいという要望でした。そのためには、重心を落として、流れや恐怖に抵抗するのではなく、イメージを受け入れ、冒険をして欲しいと言っていました。ナセラが語りかける「風」「流れ」という言葉のイメージを頭で思い浮かべるのではなく、自分自身の肉体の輪郭線をぼかすことで、身体と空間を隔てる皮膚をメッシュの布のように変容させ、空間と身体の境界線をなくしていく試みです。それによって、イメージを頭の中で想像するという主観的な行為ではなく、自分自身の存在を風や流れといった抽象的な存在に「Become/〜になる」することを求められます。
山海塾の場合、「〜になる」という意識は身体を空っぽの器として捉え、その器の中にイメージが入ることによって憑依、または変容して別の何かにメタモルフォーゼすることを意味します。その際、器としての身体を上から眺め、操るように意識と身体の距離を測っていくことが求められます。
ナセラは、身体という器ではなく、身体を気化させていくように私(人間・肉体)という存在を空間と混ぜ合わせることで、新たなマクロコスモスとミクロコスモスが渾然一体となった風景や現象を作り出します。身体をコントロールしようとすることを排除し、まるで複雑な山道を転げ落ちる球のようにコントロールをせず、原因と結果に任せた軌道に身を委ね、意識は離れた場所からその状態を眺めているような距離感を必要とします。
山海塾では、人間が逃れることのできない重力に普遍性を見つけ出し、人間という存在を中心に置いたのに対して、ナセラは重力という呪縛からの解放こそが普遍性と捉え、マクロコスモスとミクロコスモスの渾然一体の場所を探求していたように思います。