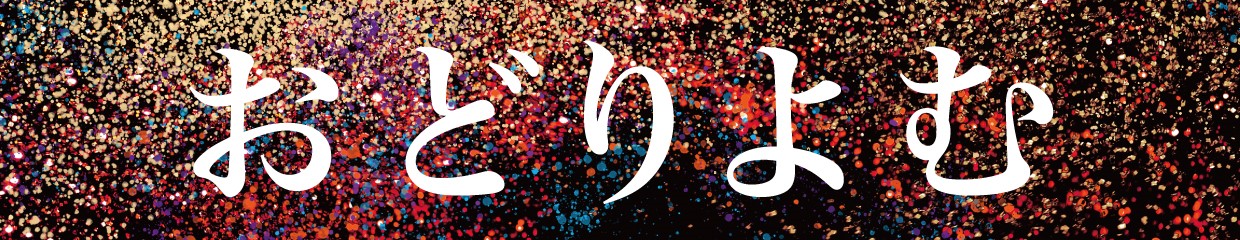「ダンスとはなにか」を問う場であり続けるために
ヨコハマダンスコレクション2023「受賞者公演」レビュー

Choi x Kang Project『A Complementary Set_Disappearing with an Impact』(Photo by Sugawara Kota)
ヨコハマダンスコレクションは、日本のコンテンポラリーダンスを代表すると言っても過言ではない国際フェスティバルである。2023年は「現象を見る」をコンセプトに、国内外のアーティストによる公演をはじめ、トークやワークショップなど、現代のダンスを巡る様々な企画が横浜を舞台に展開された。1996年の初開催から29回目を数える今日まで、この祭典の中枢を担うのが公募型コンペティションだ。旧バニョレ国際振付コンクール(フランス)の日本プラットフォームとして始まった本企画は、若手振付家の発掘・育成を目的に、これまで500組以上のファイナリストを輩出してきた。現在は国内外を問わず開かれたコンペティションI、そして日本在住の新人振付家(25歳以下)を対象としたコンペティションIIの2つがあり、映像・書類審査を通過したアーティストたちが歴史ある舞台に上がる。若手振付家に賞を授与して「発掘」し、今後の創作活動に向けての支援や公演機会を提供することで「育成」する。その躍動的な循環プロセスに観客も立ち会えること、それがこのフェスティバルの心臓部である。近年はコロナ禍の影響で海外から来日が叶わなかった例もあるが、今年のコンペティションIでは5カ国8組のファイナリストが横浜の地で作品を発表した。そんな熱気冷めやらぬなか行われたのが、Choi x Kang Project、ワン・ユーグァンの2組によるダブルビルのコンペティションI受賞者公演である。

Choi x Kang Project『A Complementary Set_Disappearing with an Impact』(Photo by Sugawara Kota)
Choi x Kang Projectは、韓国国立現代舞踊団で活動していたチェ・ミンソンとカン・ジンアンが2015年に始動させたソウル拠点のプロジェクトグループだ。今回上演された『A Complementary Set_Disappearing with an Impact』は、2018年の審査員賞受賞作『Complement』を基に翌2019年に初演された。「視界に映らないものはコントロールできるか」という問いを起点に、舞台上で生身のダンスとそれを撮影する・された映像が並走する。
客席に足を踏み入れると、舞台空間の右手にあるモニターに目が向く。舞台を客席から捉えた様子が映し出され、舞台の中に更に舞台があるという、この作品の持つ入れ子構造が暗示される。メトロノームのように焦燥感を煽るサウンドが鳴り響くなか、2人のダンサーが舞台に現れ、カクカクとした体操的でリズミカルな動きを反復する。その様子はビデオカメラを手にした3人目の出演者によって撮影されている。モニターに映し出される映像は一見生中継のようにも見えるのだが、本来映っているはずのダンサーの姿が消えるなど、それが既に撮影済みであることが明かされる。一連のシークエンスが終わりを迎えると、今度はたったいま撮影されたばかりの映像が再生され、ダンサーはそれに同期するようにパフォーマンスを開始(再開)する。つまり上演・撮影・再生が同時進行する過程が更に反復されるのである。回を重ねるごとにモニターで再生される映像、そしてその隣で展開する生身のダンスとの差異は広がり、縦横無尽に動くカメラの目を盗むように新たな身振りが加わっていく。全容を把握するにはダンサーの姿を追うだけでは十分でなく、かといってモニターに依存しても理解できない。観客の眼差しは四方八方に分散せざるを得ず、それは徹底的に誘導されるとも言えるし、同時に放置されているとも言えるだろう。2次元/3次元、見えるもの/見えないものといった二項対立は、徐々に見なくてもいいもの、若しくは見えていないとされるものによって侵されていく。終わりなき反復運動は観客の記憶を上書きしつつ、次の展開を歪に予感させる。既に振付られた(撮影された)ことを遂行・再現する様子、或いは振付する/振付られる人や物の均衡が崩れていく光景は、ライブパフォーマンスならではの躍動感に満ちていた。

ワン・ユーグァン『Beings』(Photo by Sugawara Kota)
台湾の振付家ワン・ユーグァン率いるShimmering Productionによる『Beings』は、2021年12月に奨励賞、アーキタンツ・アーティスト・サポート賞、城崎国際アートセンター賞をトリプル受賞した作品である。今回の受賞者公演後にはアーキタンツで新作を発表し、その後は城崎国際アートセンターで滞在創作を行なった。このような横浜だけに留まらない活動の広がりは、受賞がゴールではなくスタートとして機能した理想的な例と言えるだろう。また、受賞当時はコロナ禍の影響で映像上映による審査を余儀なくされたため、『Beings』は待望の劇場上演となった。「人」という漢字や書道、そしてインクと紙の関係性から着想を得たというデュオである。
漆黒の闇が広がる舞台の中心に光が射す。朧げに浮かび上がるのは、雑然と丸められた巨大な白い紙。そしてそれを抱える人の姿。その4メートル四方の手漉紙が広げられると、もう1人のダンサーが表れる。仮初めの舞台ならぬ紙の上で、光と影が繊細に移ろうモノクロームな世界が立ち現れる。2つの身体は紙を介して遊戯的に戯れたかと思うと、拮抗するように親密なコンタクトを繰り広げる。時に外の世界に手を伸ばすように身体を開くが、互いの間に強い引力があるかのように引き戻される。ふと足元に目をやれば、どこからか黒いインクが肌を伝っており、それは次第に2人の身体に影を落とすように広がっていく。実存を問う深遠なテーマが根底に横たわりながらも、動きは一筆書きのような淀みない美しさを讃えていた。巨大な紙は、滲んでいく黒いインク、移ろいゆく照明、そしてダンサーの動きによって絶えずその姿を変え、あたかも第三の登場人物のような存在感を醸し出す。それは作品の出発点である漢字や書道のイメージと分かち難く結びつく一方で、紙というマテリアルとの戯れそれ自体が作品の主題を担う、そんなまた違った見方や展開が生まれる可能性を秘めているように感じられた。現在創作が進められている三部作『A Trilogy — Quest of Relationships』の最初のエピソードにあたるという本作、今後どのように発展するのか期待したい。

ワン・ユーグァン『Beings』(Photo by Sugawara Kota)
今日の「コンテンポラリーダンス」という言葉で編まれた多種多様な表現は、絶えず既存の価値観が問題視され、更新されてきた結果だと言えるだろう。全く異なるダンス観を提示する両者のアプローチからは、コンペティションが「ダンスとはなにか」それ自体が問われている場所だと再認識させられた。それは同時に優越を付けて評価する困難さ・複雑さと向き合うことでもある。近年は賞を複数設けることでアーティストを激励し、同時期に開催される横浜国際舞台芸術ミーティング(YPAM)との相乗効果により、アーティスト、プロフェッショナル、そして観客が行き交うダンスのプラットフォームとしての傾向が強まっている。しかし、それはコンペティションであることの必然性の揺らぎではないだろうか。オンラインで世界とダイレクトに繋がれる機会が増えた現在、日本と海外のダンスコミュニティの架け橋を担ってきた役割も変化しているように思われる。また、メディアを通じてダンスの様々な形式・側面に触れられる昨今、ここでの「作品」とは狭義なものである。応募するためには上演時間を20分以内に収める必要があり(コンペティションⅡは10分以内)、劇場空間での上演を想定しなければならない。アーティストはその制約を生かし、むしろ逆手に取ることを求められる。しかし、コンテンポラリーダンスの現れがダンスの新しい価値を更新し得るものだとすれば、まだ見ぬ新しい振付言語の開拓は、既存の制約や評価軸を踏襲することで促進できるのだろうか。アーティストだけでなく、どのように枠組みを作る側も価値観を新たにしていけるかが問われているように思われる。この歴史ある場がより「振付とはなにか」、そして「ダンスとはなにか」を問う場であり続けてほしいと願ってやまない。