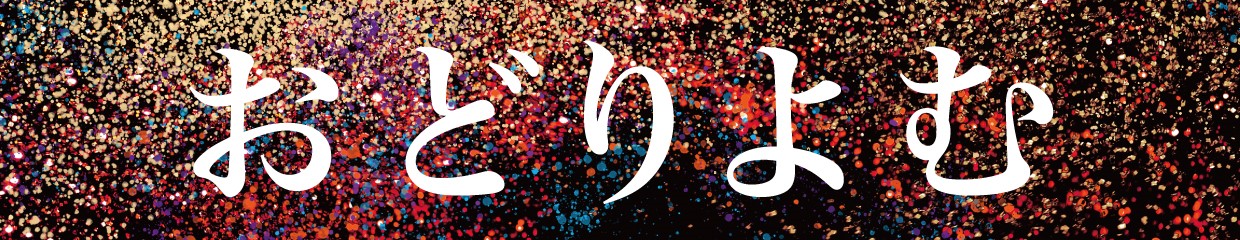鎮魂への祈り
中川絢音<水中めがね∞>『しき』レビュー
ヨコハマダンスコレクション受賞者公演『しき』(演出・振付=中川絢音)はリクリエーションというよりは、シリーズ第2弾と呼ぶべきものだろう。2021年の日本舞踊家との初演は、身体を弔い葬ることをテーマとしたものであった。今回、岩本大紀、岡本優、小川莉伯、LINDAと水中めがね∞の金愛珠、根本紳平、中川絢音の総勢7名で演じられた舞台も、テーマとしてはその延長線上にある。古代ローマ人の死生観を示すラテン語の墓碑「NF F NS NC −我かつて存在せず、そののち存在し、いまは存在せず、思い悩むことなし」から着想を得たという本作は、死だけでなく生の根源的なあり方にも着目する。日本舞踊に加え、舞踏やバレエ、朝鮮舞踊、アニメーションダンス、僧侶の修行などを経た身体が、コンテンポラリー・ダンスの枠組ならではの、自由で豊かな空間を物語る。ここでは舞台に見えた物語の一つを書いてみたいと思う。
喪失あるいは誕生
上手上方から光が差し、舞台中ほどに斜めに倒れた墓碑のようなものに頭をつけて立つ和装姿の女が、仄暗い灯りに見えてくる。脈打つような低い音楽を超えて、女の呼吸音がやがて有声になり、それがだんだん早くなって大きな叫びとなって暗転する。女は大切な人を失ったのであろうか。喪失感がその立ち姿から伝わってくる。その喪失は、あるいは新たな生の誕生なのかもしれない。

Photo by Sugawara Kota
復興と成長
再び明るくなると、上手奥に白装束の女が横たわっているのが見える。叫び疲れて息絶えてしまったのだろうか、微動だにしない。墓碑のように見えたものは金属製の衝立で、舞台中央にある。その周りを白い道着のような衣装の男女や空の台車が行き交う。下手から登場するスイーパーを持った女が、床に手をつき片足をスイーパーに対して直角にあげてポーズをとる姿が印象的だ。人々は時々、物になったかのように固まる。パントマイムやストリートダンスでも多用されるこの留めのポーズは、人間が物質であったことを思い出させる。その固まった人物を、別な人が運んでいく。奥に横たわっていた女性も持ち上げられ、足が地面についた途端、動き出す。生きる中で人は人材となり、物質として世界の歯車となる。行き交う人々の中、金属の板が運び込まれ、衝立に側面が付き、正面の扉が電動ドリルでビスドメされ、箱になる。
このシーンはまるで街の復興現場を見ているようだ。出来上がったロッカー状の箱は下手に運び出され、すぐに上手から同じような箱が担ぎ込まれ、中央に据えられる。すると台車に乗った僧侶のような男が、白装束の女に押されて登場する。様々な印を結ぶように手を動かす男は、復興された都市の家々やビルの建立を寿いているようにも見える。

Photo by Sugawara Kota
遍歴と昇天
場面が変わり、二人の男に担がれた箱が、三人の踊り手を従えて練り歩く。道中で出会った人は一瞬驚いたように立ち止まり、列に加わって踊り始める。さして広くもない舞台で箱を担いで移動するだけで道行のように見えてくるのは、ひらひらと舞う手足におのずと目がいく踊りが、どこか神輿担ぎの囃子のように見えるからか。
箱は目的地に着いたのだろう。中央に直立して置かれる。反対派だろうか、居合切りのような所作で男が一人、何度もこの箱に挑みかかる。周りでは冒頭の場面と同様に、スイーパーを持って倒立片足あげでポーズをとる人や、空の台車を押す人、固まった人を移動させる人らが行き交う。箱に挑んでいた男が諦めた頃、男と女が箱に近づき、箱を横たえる。観客席に背を向けた女は、正面から箱を開ける。箱からは光が差し、その光はだんだんと強くなる。
この箱は鎮魂祈願のご神像か何かで、光は御神体が宿った印なのだろうか。それとも、非業の最期を迎えた人々の魂が箱を依代に集まってきているのだろうか。どこからともなく笛や鼓や囃子方の掛け声が聞こえ始め、人々は箱を囲んで踊り始める。ダンサーらも時に掛け声をかけ、その踊りはだんだん速く激しくなり、それに伴い笛の音も鋭くなっていく。腰を幾分落とし、指先まで神経の通った踊りは、次第に重心が下がり始め、コサックダンスのように座った姿勢からの足の伸曲を繰り返し、ついには転がり始める。手先や手首、甲の反りや足先を表情豊かに動かす舞踊は、日本舞踊だけでなくインドの宮廷舞踊など、どこかアジア的なものを想起させる。
この奉納の舞が十分御心に叶ったのだろう。天からビーズのような白い小さな米粒がザーという音を立てて箱に降り注ぐ。明らかにその粒は上から下に落ちて来ているのだが、それはまるで冒頭で失われた多くの人々の魂が天に成仏して昇っていくように見えた。

Photo by Sugawara Kota

Photo by Sugawara Kota
『しき』の上演で語られる言葉はなく、上記は観客である筆者に見えた物語にすぎない。とはいえ、それは単なる妄想ではなく、ダンサーの動きや照明や音楽によって創造された空間が喚起したイメージである。
上演から受ける強い祈りのようなメッセージは、その対象が日本に限定されるわけではない。冒頭の場面は能登半島地震や東日本大震災の喪失の場面にも見えたが、遠いガザやウクライナの戦争で亡くなった多くの人々の嘆きにも、またそのような世に生を得た悲鳴にも見え、その後に続く場面はそれら全てへの鎮魂としてあり、最後の奉納舞で昇華されたようにも感じられた。

Photo by Sugawara Kota