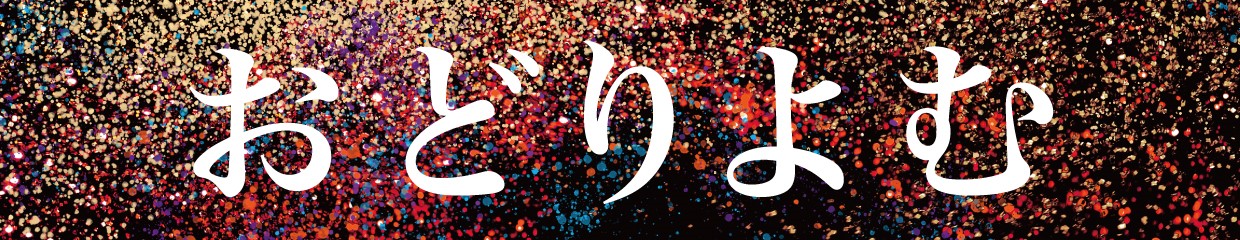身体のローカリティーここから
ダンサーのAokidです。
私が初めてヨコハマダンスコレクションを観にいったのは2007年。
その時見たショーケースの中でとりわけ覚えているのは、川口ゆいによる映像や単管の組み上がった構造体、椅子といったオブジェクトと超絶技巧のバレエベースのダンスが舞台上でミックスされる作品でした(『REM – The Black Cat』)。別々の要素が舞台上に並び提示され、それらが断片的なポエムとしてあるいは空間を変容させる“ダンス”として複層的に経験されるようで、それまで私が主に知っているストリートダンスの5分ほどのショーケースやバトルなどによって経験される身体表現とは全く異なるものでした。
それに続いて2008年に、舞台での観劇こそ叶わなかったものの赤レンガ倉庫2Fスペースで振付家を紹介するブースの中にKENTARO!!によるダンス映像を見つけました。自分と同じくストリートダンスをベースとしながらも換骨奪胎し切って全く見たことのない表現としてストリートダンスのテクニックが180度曲げられた状態、豹変した表現に強く影響を受けました。

川口ゆい『REM – The Black Cat』(2007) Photo by Tsukada Yoichi
それから数年間ダンコレに通い詰め、たくさんの国内外のダンスを見てはアンケート用紙の裏側にまで感想を書き込むほど、舞台や作品について考え、まとめて知ることの出来る機会となっていきました。ショーケースという枠組みで様々な作品を比較することで“コンテンポラリーダンス”のバリエーションを理解していくようになったと思います。
やがて段々とアジアの作品のエントリーも増えていき、日本の作品群との傾向の違いなども感じるようになりました。何か日本のものは演出などによって作品の見せ方が表面上、上手いと感じられることが多く、たとえば東南アジアとかであれば日本とは別の違う基準や方向性が採用されているような作品に出くわすことが多く、結果的にそれらの鑑賞は作品として共感出来たり、自分の興味を刺激するものではありませんでしたが異なった文脈や身体がダイレクトに、あるいは伝統舞踊との距離感などを読む機会のようにして経験されました。

Aokid×橋本匠『フリフリ』(2016) Photo by Tsukada Yoichi
それからさらに数年経ち、2016年に自分たちの作品(『フリフリ』橋本匠[→現たくみちゃん]との共作)で参加した後は忙しくなりこれまでのように通うことが難しくなりました。
今回この依頼を受けたことで2週間で20本以上(ダンコレ以外も含め)の作品を鑑賞する機会をもらいました。
いくつか印象に残った作品について触れたいと思います。
コンペティションⅠ(2日目)でのファイナリストasamicroによる20分ほどの上演。
この日の上演では彼女の取り組んできたダンスを何の衒いもなくそのまま受け取れたという感想を持ちました。コンペという場において作品の上演が目指されたにせよ、そこで起きていたことは率直で、彼女の現在のダンスを見るという意味に限らず、これまで彼女が踊ってきた事実が前面に現前化しているように感じられました。全ての振付に意味がついているように、そしてその一つ一つが自然に理解されることが叶うように客席の私には感じられ、こんな経験は一年に数回あれば良い方で、毎回こんな観劇はおそらくは体験出来ないと思います。
彼女を含めKENTARO!!の登場以降、様々なストリート出身のダンサーがエントリーするようになりました。今作はその中でも意識的にストリートダンスのステップがプレゼンテーションされるシーンもあったと思います。作家によってアプローチや態度が違って、そのことについて言及し比較していくのもあまり手をつけられていないと思いますが、面白い作業かもしれません。

asamicro『Wake up』 Photo by Sugawara Kota
のげシャーレで観たP.A.R.T.S出身のフランス人作家のジョルジュ・ラバット。
限りなく裸に近い格好をした作家本人は自身の身体に近い半透明な人体彫像を用いて、タームごとに分けられた時間を使ってゆっくりたっぷりとそれと戯れていきます。静止した形として完結した動かない人体彫像を丁寧に移動、空間に移行させることでまるで自分の身体の側が空間を移行しているような逆さまの錯覚が一瞬感覚に生じます。
とは言え悠長でもあるその前半のやりとりは、上演よりもパフォーマンスアートとして自由に鑑賞することができれば飽きずに見られるのではという考えがよぎります。
しかしもう少し見ていき、後半で彫像を抱え持った止まらない回転運動が始まります。メリーゴーランドのようなゆったりした回転からやがてコーヒーカップの二重回転のようなスピードで彫像と見つめ合いながら回転し続ける2人の姿。それがまるで“自分と他者という関係”から“鏡に映った自分を抱え込んだ同一の1人の人物”というような姿として回転高速運動によって錯覚が起きていきます。
回転高速運動の中では、人とオブジェクトを切り離した単体としてそれぞれに見ることが難しくなり、ひと繋がりの塊として認識されました。
主体と客体の反転についてのテキストが配られましたが私は一連のこの様子を見ていて、まるで相手を想像し行われていたはずのマスターベーションがこの回転運動によってむしろ限りなく自分に向かい求心していく想像が強く掻き立てられるようだと思いました。
相手への強い眼差しがむしろ自分に向いていたとわかるような感覚。また回転する運動はここを“地球”であると認識し、そして地球の回転を中心に全宇宙がマスターベーションを助けているように思えてくるのでした。
全く共感出来ない客席の一部は置いていかれ、私は全く彼(ら)に魅了されそれに釘付けになっていました。
またこの作品(『SELF/UNNAMED』)は劇場における座席の拘束性とも極めて親和性が高く、自覚的に作られた作品だと思いました。

ジョルジュ・ラバット『SELF/UNNAMED』 Photo by Ohno Ryusuke
小㞍健太は建築家や音楽家とのサイトスペシフィック作品を上演(『Engawa, Imaginary Landscapes』)。
最初、観客たちは壁に沿って敷かれた向こう側へと伸びていくパンチカーペットの敷かれた廊下の両脇で待たされ、そこから1人のダンサーが片側の入り口から入ってきて扉が閉まって上演が始まります。そこに集まった人の形などをまるで根拠にするようにして踊っていき、観客の身体ごと一緒に上演の身体へ作り変えられるような緊張感やゾクゾクした感じがありました。今度は向こう側に案内され、観客たちのぞろぞろと歩いて向かっていくその足取り自体が、背後から追う自分には渡り廊下を歩く時のように美しく感じられました。
案内されたスペースには何か流木を想起させるような角材が頼りなく立ち、別のダンサーがおそらくその形にインスパイアされているような踊りを展開します。先ほどの対人に対して今度は対オブジェクト。それらの経験などが積もり、次の展開への期待がありましたが段々と作品は前方のスペースでの3人のダンスに向いていきます。
最初のダンスのしつらえが空間や人といったものと丁寧に段階を踏んで関係を築いていったのに対して、横長の舞台とわかる前方のスペースで動きが展開した時にこれまでの広さを持て余したまま見ている感覚がありました。鑑賞する場所にも関係していたのかもしれません。
たとえば、ここで音楽が決まった場所にあるスピーカーから空間への効果でなく生演奏などで場所を変えながらダンサーや観客への影響を恣意的に与えられるものであったなら、私が鑑賞した場所からであっても先ほどまで積み上げられた広い空間との関係の中にダンスを見られたかもしれないと勝手な想像をしました。
捩子ぴじんによる長いダイアローグを軸とした作品(『ストリーム』)も、後半に結実するようにナラティブであることと冗長であるということが組み合わさってとても強い印象を残しました。

捩子ぴじん『ストリーム』 Photo by Sugawara Kota
上記に挙げた作品群やパンフレットからもわかるように“上演”という方法を使って、レクチャーパフォーマンスの要素のあるものや、複数のスタイルの融合、バンド演奏付きのダンス上演、客席と舞台をフラットにした状態での上演など様々なバリエーションが並ぶラインナップであったにもかかわらず以前のように、客席でそれらの作品を見ることに充足感を感じませんでした。色々な試みを見たはずなのに非常に狭い範囲のダンスを経験しているように感じさえしました。(他の場所でそれぞれの作品を観ていたら違ったかもしれません。)
かつて舞台を通して見ていた新しい表現や別の地域性といったオルタナティヴ性を今回はなぜか強く感じられませんでした。見れば見るほどどこか徒労感や閉塞感みたいなものを感じていました。
その理由について考えてみます。
自分や社会のことを個人的に仮説をたてて振り返り、考えてみたいと思います。
20年ほど前、私が観客として舞台に期待していたことは上記のように自分の取り組むストリートダンスとは対をなすようなオルタナティヴなアイディアを見ることでした。
2010年前後から作品を作ることと並行し、屋外でのパフォーマンスを重ねたり、他分野である演劇や美術、音楽の催しを見たり、影響を受けて自分でもオルタナティヴなイベントを始めたりしました。そういった中で劇場のショーケースというのも数ある可能性の一つだということに気づいていきます。
やはり劇場の主な役割は基本的には“上演”にあり、ダンスや演劇を中心とした“舞台芸術”自体は別の地平での活躍が進んでいる一方で、劇場で扱える領域が極めて限定的であるということへの言及自体がまだ少なく、そういった違和感がどこか自分の中にあるのかもしれません。
コンテンポラリーダンスのコミュニティに期待したいのはより広い範囲で偏在する“ダンス性”や“身体”みたいなものを発見し、あるいは許容し続け、流動的に広がり続けるようなことに一緒に取り組む場であってほしいということかもしれません。
付け加えて言うなら、これまでに様々な方法を新たに発見し舞台上にあげることを叶えてきた人たちがこれだけ集まるフェスティバルという場において、誰かの上演を鑑賞し事後的に記事としてまとめるに留まらず、この“人が集まるということ自体”に何かを託し、作っていくような方法があるのでは、という予感かもしれません。たとえば一人の作家の上演を叶えるという形式以外での、これからの“ダンス”がどのような形をもって社会の中に存在してみられるかを試すような、、、

Dance meets Dance:世界装置パフォーマンス Photo by Kumagai Yoshitomo
ここ10年ほどでスマホやSNSによって社会における映像メディアのあり方は変化していきました。当時であれば屋外などでパフォーマンスをする人は一部でしたが、スマホやSNSが一般的に普及していく中で街の至るところで撮影を目的としたアクションが増えていったように思います。またその撮影とSNSでの発信を頼りにそれを表現の場として、様々な場所でアクションする光景も増えました。そういった中で「劇場とはダンス上演を受容することが出来る場所」ということの価値も変化していったように思います。表現する場所やメディアが増え、圧倒的に表現をする風通しは良くなっている状況の中で客席の拘束性や、タネも仕掛けもある劇場の有効性とはどのようなことなのか。
ジョルジュ・ラバットの作品は極めて客席の拘束性に自覚的だと思いました。客席の拘束性に関しては、やはりアジアよりもヨーロッパの作家の方が自覚的だったり、それ自体をコンセプトに内包している作家は多いのでは、と推測します。
また専門的に書き切ることは難しいのですが、西洋の劇場というのは当然日本のように近代になって文脈もなく登場したわけでなく歴史の文脈の中で街の一つの機能として作られたということもあり、街の文脈ともずっと接続している強さがあるのではと推測します。
コンペティションⅠで審査員賞を受賞した韓国のデュオ作品(キム・ナイ、チョ・ヒョンド)はストリートダンスをベースとした質の高いもので、あまり日本では見かけない作品の印象を受けました。が、どこか既視感もあるような、しかしテクニックベースで広がっていくような強さは日本とのディレクションの違いにも関わってくるのではないか、とHOTPOTなどの韓国作品も見て総合的な感想を持ちました。

キム・ナイ、チョ・ヒョンド『Nonfiction』 Photo by Kumagai Yoshitomo
またダンコレの他にYPAM期間中に篠田千明によるインドネシアとのコラボレーション作品「まよかげ/Mayokage」や、Murasaki Penguinがシンガポールのダンサーと制作した「Dove Lake + Aqua Line」をそれぞれ観ました。単独公演ということもあり、彼らは自分たちの表現を劇場、客席から作ることに成功していたように思います。
ショーケースという性質上、毎回の作家たちとの公演でいちいち客席や劇場から作品を作ることは難しいでしょうが、どうすればフェスティバル自体を有機的にしていけるかという思いで、上村なおかさんとヨコハマダンスコレクション企画「Dance meets Dance」というプログラムに取り組む機会をいただきました。
それはワークショップやトーク、ショーケース、DJタイムなどを赤レンガ倉庫2Fスペースや3Fホワイエを使って展開するというものでした。コンペティションを鑑賞して帰るだけじゃなく、長く滞在し、人と話したりワークに参加したり、見たものの感想を言い合うことでその空間や時間を有機的なものにしようというのが狙いでした。

Dance meets Dance:カラダを描く カラダで描く Photo by Kumagai Yoshitomo
たとえば数十年前であれば舞台上に何を提示するかが“コンテンポラリーダンス”の多くの部分を担っていたと思います。が、そのことが時代とともに変化してきているタームなのではないでしょうか。
しかしダンコレのアーカイブやネットワークからもわかるように多様な作家の多様な取り組みがこれまでもありました。段々とそれらの表現が舞台上で更新されていったように、実は客席にいたはずの観客としての表現も更新されているのではないでしょうか。
たとえば上に挙げたような各地での生態系のような多様な取り組みに触れていくこと自体をダンスのように捉え参加していくことで、もう少し互いに信頼を寄せ、向かうべき方向性を検討するようなこと、フィードバックまで起き、それらが一連のこととして動きの中で出てくることさえあるかもしれません。
劇場の“上演”が続きながら、こういったオルタナティブな価値観を積極的に広げていくことが出来るのかはわかりません。が、何度も同じように集まってきたこの小さなコミュニティは、考えようによっては、これからももっと別の何かに取り掛かることは出来るんじゃないかと、いつもどこかで思ってしまいます。
果たしてそれが結果としてどうなるのかはわからないのですが。
確かに“上演”においては、昔から観てきた人が言うように以前よりも何か刺激がなくなったとか、そういうのはあるかもしれませんが、それは舞台だけでなく社会も世界も自分も変わってきていることと関係ないはずはないと思いますが、一方で明らかに、“コンテンポラリーダンス”やその作家たちやダンサーたちや関係者たちが扱い、共有し、話している領域はまた広がってきているという風に私は感じています。
そんなことまで引き受けるの?っていう部分まで“ダンス”や“身体”、“関係性”として取り上げ、取り掛かる姿をたくさん目にしている気がします。
つまり端的に言うと、ショーケースだけをさしてコンテンポラリーダンスだ、と言うのではなく、“コンテンポラリーダンス”(を通した考えなり心意気?)が引き受ける領域が今日、また更新され実はとても広がっていったということを面白がり、それで未来が開かれていくのではないかと考えます。
出来るだけ“ダンス”を有機的な鮮度を持って伝達し続けたい、です。

Dance meets Dance:DJタイム Photo by Kumagai Yoshitomo

Photo by Kumagai Yoshitomo