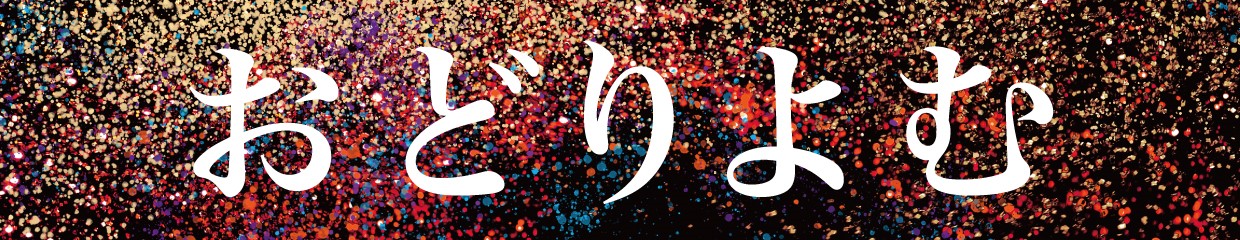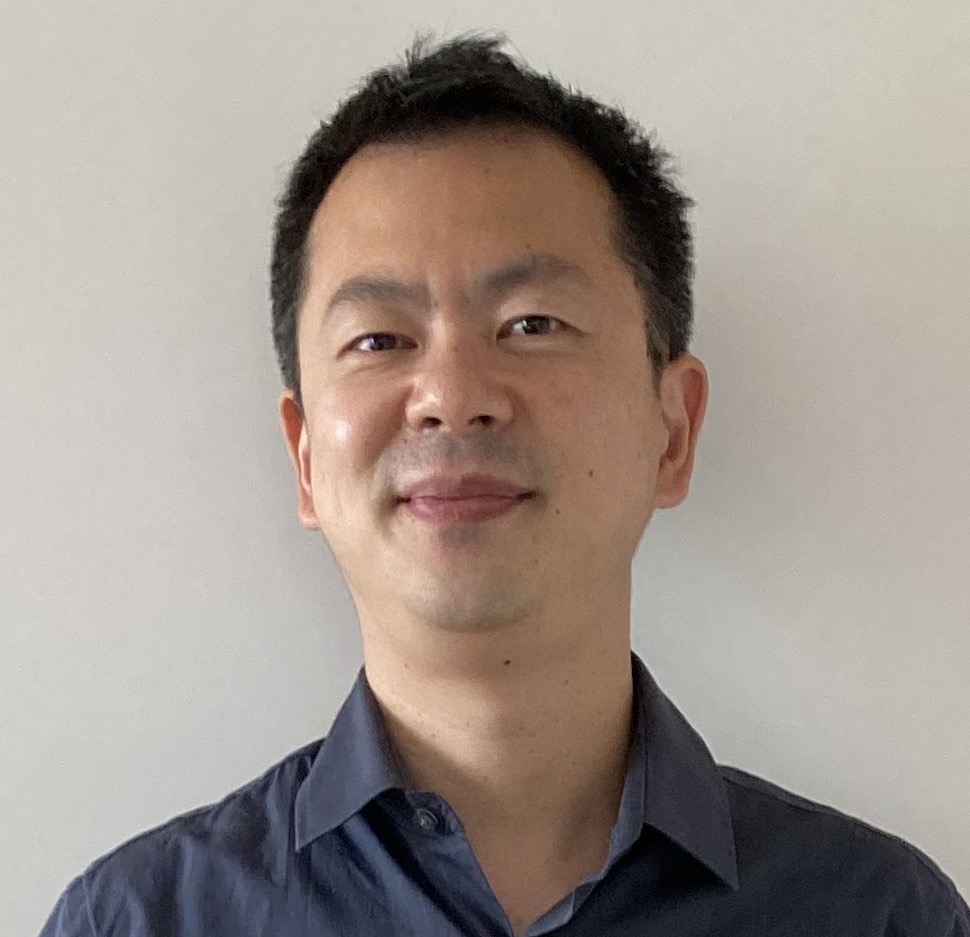スペクタクルとノンダンスのはざまで
小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『再生』レビュー
「演劇に行こう」──という特集が組まれた2018年11月号の『現代詩手帖』を近所の古書店で偶然手にとった。小野と中澤はそこで、「演劇とはどういうものであるか」というきわめて素朴な質問に対し、「人が表現する芸術で一番、人に寄り添った芸術だと思います」(小野)、「観客が芸術家になる瞬間ももっともっと身近で当たり前にしていくことができたらいいなと思いながら、最近は人間対人間の芸術ということにして扱っています」(中澤)と答えているのだが、おそらくいま、この「演劇」を「劇場」と言い換えてみても、差し支えないように思える。彼らの「ダンス」もまた人に寄り添う、対人間の上演にほかならないからだ。
スペースノットブランクは、小野彩加と中澤陽という二人の舞台作家のコレクティブである。彼/彼女らは『バランス』という作品によって「ヨコハマダンスコレクション2022 コンペティションⅠ」を受賞したのち、2024年5月から7月にかけてフランス国立ダンスセンターでのレジデンスを行った。そして帰国後、2024年12月に初演されたのが『再生』という作品である(12月2日・3日=横浜にぎわい座のげシャーレ、12日〜14日=神奈川県立青少年センター)。

Photo by Ohno Ryusuke
本作は、2006年に初演された東京デスロックの演劇的作品が元になっている。この場合の「元」がどういうことかは、多田淳之介自身が、スペースノットブランクのホームページに寄稿をしているので参照していただきたいが、ひとまずスペースノットブランクは「30分の物語を3回繰り返す」という原案の構造を継承しながら、これをまったく別のグルーヴィーでセンチメンタルな作品に換骨奪胎した、というのがあらましだ。
多田は『再生』を、2011年の東日本大震災を受けて『再/生』として再創造し、さらにそれを『RE/PLAY DANCE Edit.』(2014年)という国際共同制作のダンス作品に変貌させているが、小野や中澤がどの段階の上演に立ち会っているかは定かではない。ただし、ジェローム・ベルから『ピチェ・クランチェンと私』の構成を受け取り、その翻案として『松井周と私たち』(2023年)に展開させたスペースノットブランクにとってみれば、オープンリソースともいうべき「形式」としての上演の伝達、解釈、継承というズレを許容してくれる多田の包容力は重要なファクターであっただろう。

Photo by Ohno Ryusuke
本作は、薄暗いブラックボックス式の舞台で、ギターの弾き語りから徐ろにはじまる。かつて〈重力/Note〉に俳優として参加していた瀧腰教寛によって歌われるのは、ゆるやかでユーモラスで、少し淋しげな「街は水族館」という曲だ(歌詞は当日パンフレットに記載)。《海、川、みずうみ…》という歌詞=テクストは、ギターの音色と、瀧腰の哀愁漂う声と混じりあいながら、暗闇の空気のなかに消えていく。おでん屋台の主人と他愛のない話をしたあと、ひとり夜道を帰る心地よい時間のようだ。
『再生』は先に述べた通り、「30分の物語を3回繰り返す」作品である。ゆえに必然的に、瀧腰の弾き語りも上演中に3度繰り返される。瀧腰がギターをおろして指をパチンと鳴らすと、若きUAのハイでソウルフルな曲(『太陽手に月は心の両手に』1996)が流れ出し、ダンサーたちは列をなしながら、思い思いに踊る。その後も、aikoの〈君にいいことがあるように〉という無条件の祈りが無限に繰り返されるかのような曲(『ストロー』2018)、アジアの民謡風の曲、メタル風の曲などへと次から次へと曲調を変え、それに伴ってダンサーたちは「同じ」動作を行う。創造過程については、白尾芽によるレビューも公開されている(「疲れるのは誰?」)。
作品の趣向は異なるが、わたしは、ジェローム・ベルの『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』を思い浮かべていた。舞台上のさまざまな出自をもつ「ダンサー」たちが、「ダンス」に関わる指定の楽曲に合わせて、公募キャストが一列に並んで自由に踊るという作品で、日本では、2011年11月にさいたま芸術劇場でも上演された。もちろん、3度の反復がある『再生』において、ダンサーたちは「同じ」振付で踊るのだが、しかし振付は個別的で、それぞれが独立した象形文字のようだ。実際に、30分のセットの最後には、7名のダンサーたちが人文字で「REBIRTH」を形作るという遊び心もある。

Photo by Ohno Ryusuke
先ほど触れた東京デスロック版が「REPLAY」であるのに対し、本作の英語タイトルが「REBIRTH」となっていることは、作品モティーフにも関わっているのだろう。リバース。フランス語でいえば、ルネッサンスだ。英語の「REPLAY」が、「演劇・遊戯Play」を内包しつつも、録音・録画の「再生」を意味するのに対し、「REBIRTH」は、生まれ変わること、死生観によっては「転生」することを表す。
かつて「なろう系」と呼称されていた、いわゆる「転生もの」の流行は今なお続いているが、それはかつて宮台真司が語った〈終わりなき日常〉を生きる「知恵」のひとつなのだろう。ラノベやマンガ界隈では、「絵」という空想的な力に依拠しつつ、記憶(精神)を保持しながら、別の身体を受肉する(『転生したらスライムだった件』2013-2015)。近年のドラマでいえば、『愛の不時着』(2019年)にせよ、『不適切にもほどがある!』(2024年)にせよ、現実では越境が困難な時空を乗り越えることによって価値観が相対化され、人物たちが「成長」するという社会的なビルドゥングスロマーンが埋め込まれている。この視点から見れば、社会的な話題となっている「ホス狂」も「闇バイト」も「オンラインカジノ」も、本質的には同じ現象だ。
だから、スペースノットブランクの『再生』は、多かれ少なかれ自らの「生」の意味を求めつづけてしまう「私たち」への挽歌のようにも見える。しかしダンサーは、肉体や時代や国境を乗り越えることはできず、みずからの身体を生きるほかはない。それは絶望だろうか。退屈だろうか。原案の『再生』は、日常を「死」というモティーフによって劇的なスペクタクルにするのに対し、スペノ版『再生』には、日常を愛おしむような手つきが感じられる。わたしたちは、昨日と「同じ」肉体で今日も生きる──そのような認識のもとで、振付は基本的に過酷なものではない。ヤン・ファーブルの『劇的狂気の力』(1984年)のように、体液まみれの生々しい肉体の疲労を見せる趣向ではなく、ダンサーたちは自身の振付に忠実になれる。つまり、「無理をしない」のである。

Photo by Ohno Ryusuke
逆にいえば、ダンサーたちはそれぞれの日常を、肉体を、孤独を踊らなければならない。それこそが、彼/彼女たちに課されたタスクなのであり、その無秩序=〈終わりなき日常〉を象徴するイコンとして、瀧腰の「弾き語り」がある。東京デスロックが提示していた「集団自殺」というモティーフは常識的に反転し、「個々が生きる」という意志的な側面に光が当たることになる。とはいえ、「まったり」生きるだけではない。曲調の変化に応じて、一貫性のない日常を生きる彼らは、それぞれに「頑張って」もいる。
そのような「頑張り」の集合体として組織される社会もまた、当然ながら無秩序なものだ。今日もSNS上では、さまざまな事象に対する批判や違和感が表明されつつ、見慣れたディスコミュニケーションが話題を変えて再演され、シェルターに逃げ込むように、別種のSNSでは「生の肯定」ともいうべき写真や動画の「再生」、推しに対する共感的な語りが繰り広げられている。
たとえばわたしは今日、寝起きにラジオで柳亭小痴楽の落語を一席きき、アメリカとウクライナの政治的論争に触れ、留学中の日本人による中国語ショート動画を見て、いつ到来するかわからない株価の下落を気にしながら、日常的な業務をこなしつつ俳句をひねりだし、気晴らしに聞いた人気ミュージシャンの新曲のリズムと音程の複雑さに辟易し、『大江健三郎自選短編』を読んで嫌な気持ちになりながら、さて来月はどの日に能と歌舞伎と落語に行こうかなどと、ここのところ体調を崩しがちな子どもの心配を優先しながら、過ごしている。カオスだ。
だが、こんなわたしであっても社会の一員として生きていかなければならないように、個として踊るダンサーたちは、曖昧な関係性のなかで、お互いを意識しながら、ひとつの流れに向かっていく。30分間のなかの後半、フランスで出会ったダンサーであるというゴーティエ・アセンシは、まるで初めて体験するアジアの風土や習慣を楽しむかのように、空手の「正拳突き」のような動作をトレースし、それがやがて全員に「伝染」していく場面がある。この「クライマックス」を観客は三度見ることになるのだが、一度目よりは二度目、二度目よりは三度目と、自身のグルーヴが変化していることに気づかされる。(ちなみにこのときの曲は小沢健二の『流れ星ビバップ』2003)。

Photo by Ohno Ryusuke

Photo by Ohno Ryusuke
劇場とは、一回的な出来事が行われる場所であるといわれる。もちろん演劇やダンスも一日限りの公演でない限りにおいて、必ず繰り返されるものだ。しかし、それが「型」にならないようにと、スタニスラフスキーは役柄を「演じる」のではなく「生きる」のだと論じたし、アントナン・アルトーは客席と舞台が渾然一体となるような驚異の空間(「残酷の演劇」)を夢想した。一回性の追求は、劇場体験が神秘的で儀式的な、つまり特別で非日常的な経験となることを望む。『再生』はその意味で、きわめてブレヒト的であり、観客を「冷めつつ乗る」というモードに置く。
しかし奇妙なことに、そのモードとなった観客は、空中で儚く消え去さっていく身体の軌道や、ダンサーどうしの関係性、あるいは動作や振付の裏側にあるタスクの存在、前回との微妙な差異など、さまざまなものを眼差しながら、そこにほのかな愛情が宿りはじめることを感じる(たとえば、中盤にマイム的にダンサー二名が「窓の外を覗く」場面があるのだが、そこではわかりやすい仕方で、動きがズレていく)。一度目よりは二度目、二度目よりは三度目のほうが「よく見える」ということに加えて、「見る」という個別的な経験そのものが、愛着を孕んでいることを感じ取るのだ。スペクタクルとノンダンスのはざまで、『再生』の観客は「見ること」を見ている──わたしにはそんなふうに思われた。
「二度あることは三度ある」という諺がユーモアを含んでいるように、〈終わりなき日常〉を絶望として悲観するのではなく、愛着の対象として肯定すること。もちろん、わたしたちは孤独だ。寝覚めるときも寝るときも、生まれてくるときも死ぬときもひとりぼっちである。明日、大地震が起こるかもしれない。戦争に巻き込まれるかもしれない。それでも、今日よりは明日が少しだけよくなっているかもしれないと思えるのは、ルーティーンの力でもある。大事件と退屈のあいだで、わたしたちは今日も眠りにつく。今日という一日を明日、「リプレイする」ためではなく、「生まれ変わらせる」ために……

Photo by Ohno Ryusuke