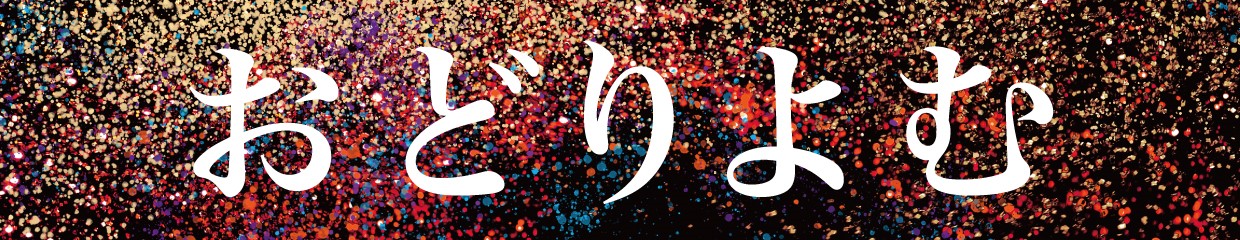振付をめぐるショートエッセイ③
上演における振付的関係――観客の経験という契機
2023.12.06
#観客 #関係性
ダンス上演において振付と呼ばれるものは、すでに書かれた記譜やスコアを示すばかりか、身体や音、光などを舞台上に配置して構成するルールとして理解されることが多いでしょう。その意味で振付は、観客が上演プロセスのうちで様々な要素を見て聞いて、すなわち経験して初めて現れるといえます。
しかし振付は上演に先立って要素の振る舞いを一義的に決めるような絶対的なルールではありません。ダンサーの身体的な動きは、スコアさえも含めた舞台上の諸要素との関係に配置されたことへの反応として現れるのであり、その動きを通じてすでにある関係(のルール)を動かすことも可能なのです。つまり振付はダンサーに対して「関係に反応することの自由」をまず与えるのであって、それこそがダンスのダイナミズムを生み出すといえるでしょう。
関係それ自体として現れる振付は明瞭に確認できないので、観客は上演の経験に基づいて自ら振付とよべる原理を見出すことが求められます。観客の経験を通じて振付が現れることで、ダンサーたちは振付に反応して踊ることができ、またその関係を動かしていくこともできるようになるのです。その意味で観客の経験は、上演に対して枠組みを与えるものであり、上演には欠かせない創造的な契機であるといえます。
振付をめぐるショートエッセイ — 6つの切り口から「振付の今」を考える —
・「動き/踊りのあるところ」(宮川麻理子) #動き #踊り
・「その足先を伸ばす前に」(宮川麻理子) #身体 #テクニック
▶︎「上演における振付的関係 —— 観客の経験という契機」(宮下寛司) #観客 #関係性
・「“Choreographies for you” —— 美術館における振付」(宮下寛司) #美術館 #空間
・「振付のフィールドとその概念の広がり、生態学的な振付へ」(吉田駿太朗) #劇場外 #自然
・「AIとダンスの融合 —— 振付の創造性」(吉田駿太朗) #AI #テクノロジー
・「動き/踊りのあるところ」(宮川麻理子) #動き #踊り
・「その足先を伸ばす前に」(宮川麻理子) #身体 #テクニック
▶︎「上演における振付的関係 —— 観客の経験という契機」(宮下寛司) #観客 #関係性
・「“Choreographies for you” —— 美術館における振付」(宮下寛司) #美術館 #空間
・「振付のフィールドとその概念の広がり、生態学的な振付へ」(吉田駿太朗) #劇場外 #自然
・「AIとダンスの融合 —— 振付の創造性」(吉田駿太朗) #AI #テクノロジー