共に在ること、共に感じること —— リヨン・ダンス・ビエンナーレ2025「FORUM」をめぐって ②
リヨン・ダンス・ビエンナーレの新企画「FORUM」について、共同キュレーターであり全体コーディネートも担ったアンジェラ・コンケとの対話から振り返る全3回の連載。
第2回では、翻訳不可能性を引き受けながら、FORUMが立ち上げた共同性に耳を澄ませていく。(第1回はこちら)
■ 関係性のキュレーション —— アーティスト間の関係、観客との関係
— 今回は5つのヨーロッパ以外の地域から、キュレーターとアーティストが参加していました。この共同キュレーションのチーム編成はどのように構想されたのですか?
私たち5人のキュレーターをゲストとして招いたのはティアゴです。そこには私たちへの信頼もあったと思いますが、それ以上に、アーティストに関する判断を他者にひらきたいという意志もあったのではないでしょうか。各々が活動する地域で培ってきた知や経験があり、それを信頼し、意思決定を分かち合う。これは、ひとりの「作者」や象徴的な人物がすべてを決めるのではない、今日的なインスティテューションのあり方を示す試みでもあったと思います。
プロジェクトが進んでいくなかで、結果的に私がコーディネーター、あるいはまとめ役に近い立場を担うことになりました。誰かがプロジェクト全体を預かり、記録し、可視化する必要があると分かってきたからです。フランス語と英語の両方を話せること、そして他の人たちよりも時間があって、議論の記録をいつも私が担っていたこともあって、この役割は自然な流れで引き受けることになりました。
いちばん大切にしていたのは、アーティストたちが、自分たちのやりたいことを、自分たちのやり方で思い描ける空間を守ることでした。すべてのアイデアを受け取り、それらが互いに響き合うのを見守りながら、テーマのレベルで編んでいくという稀有な特権を私は持っていました。だからこそ、その一つひとつのアイディアが損なわれないように守る責任も負っていました。
私たちは何かを売る——つまり上演に足を運んでもらうために人々を説得する——ことをしていたわけではありません。すべてのプログラムは無料で、かつ予測不可能でした。その特異性をビエンナーレ側にも受けてとめてもらう必要があったし、観客にもこの違いを伝える必要がありました。どれだけ立派な意図があっても、使う言葉、来場者を迎える空間、提供する体験がそれに見合っていなければ、プロジェクトとして成立しません。誰かを夕食に招くとき、料理がおいしくなかったり、テーブルを囲む空気が微妙だったりしたら、やっぱり楽しい時間にはならないですよね。だから私にとってこれは、ホスピタリティの実践であると同時に、強い責任を伴う仕事でした。
— つまり、あなたがたがキュレーションしていたのは、何よりもまず「関係性」だったということですね。
その通りです。このプロジェクトは、アーティスト同士で実践をつなぎ、分かち合うことから始まりました。招かれたアーティストたちのあいだでまず出会いが生まれ、そのあとに観客との関係が立ち上がっていった。関係に招き入れる扉が幾重にも重なって存在していたんです。
そしてそこに世界を変えようとか、何かを売ろうといった「期待」があったわけではなかった。むしろ、共に在るための別の方法を、感覚的に、身体を通して切りひらいていくこと。それは知的でもありますが、まずはともに身体で感じ取ることから始まる招待でした。ヨーロッパでよく見られる方法とは、必ずしも同じではないかもしれません。こうした異なる実践の意味を、どう分かち合えるのか——それが、FORUMで問われていたことだったのだと思います。
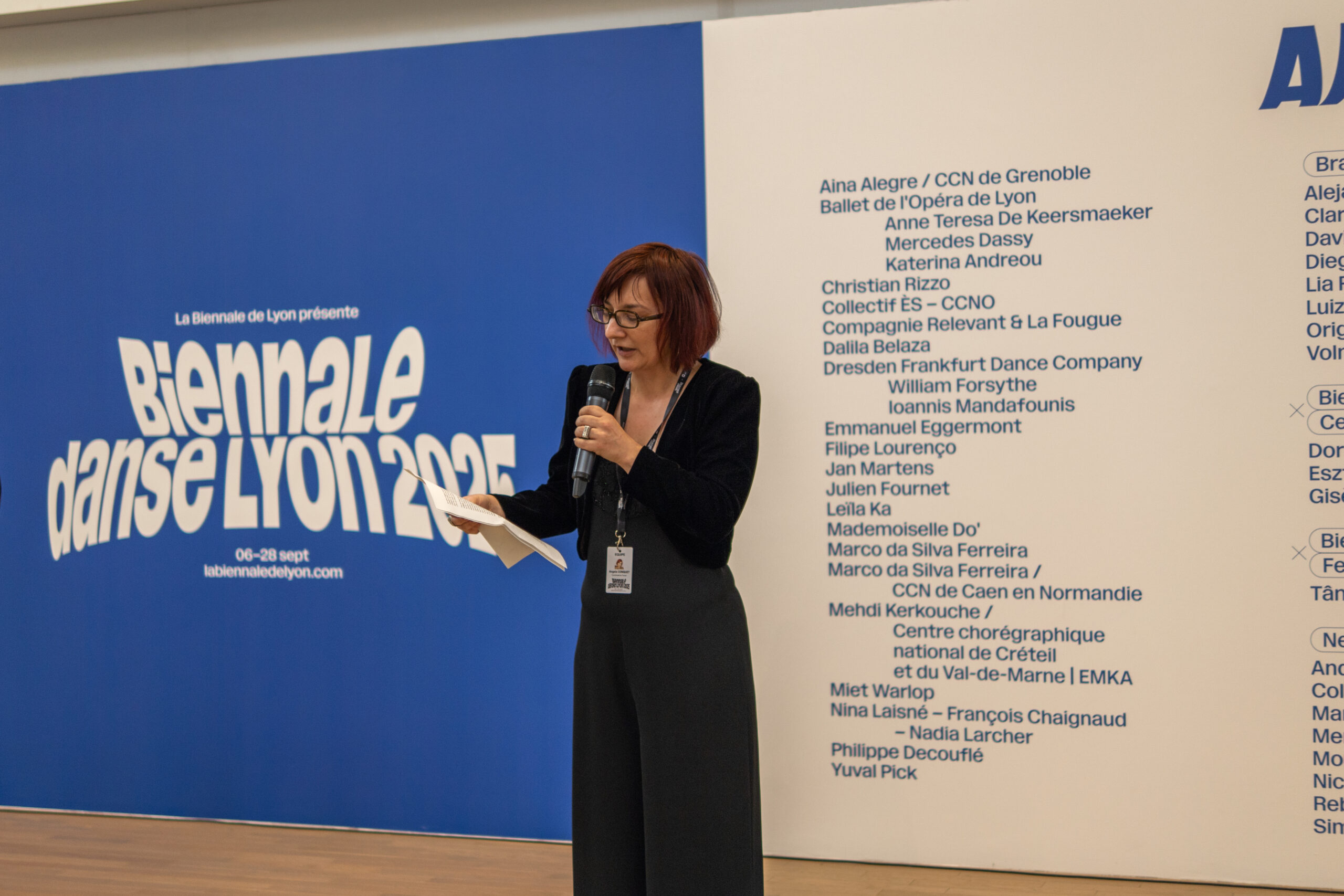
© Elyes Esserhane
■ 言語が映し出す、別の思考、想像力、身体感覚
— そして複数の言語や現実が共存する空間を構想することでもありましたね。ある意味それは政治的でもあります。
そうですね。言語はとても重要な点でした。結果的にその場には、フランス語、英語、ポルトガル語といった言語が同時に存在していました。ある若い批評家が書いていたのですが、振り返ってみると、それらはいずれも、歴史的には「植民地化する側の言語」だったとも言える。だから、最初から翻訳の可能性を常にひらいておく必要があったんです。アーティスト同士が本当に対話するためには。
モザンビークとブラジルのアーティストはポルトガル語で話すほうが自然でしたし、そうしたやり取りの場をきちんと確保する必要がありました。一方で、翻訳がなくても成立する瞬間もありました。やり取りが身体を通して行われるときです。そのこと自体が、とても示唆的でした。結局、私たちは考えずにはいられなかったんです。多くの言語が消えつつあるいま、知や経験はどの言語を通して流通しているのか。フランス語だけ、英語だけを通すということは、いったい何を意味するのか、と。
私自身、翻訳を専門的に学んできた経験があるので、このプロジェクトは非常に濃密な翻訳の実践ともなりました。たとえば、オーストラリア先住民のカンパニー マルゲクが使っていた「(Choreographic) Truth Telling」という言葉があります。「Truth Telling」は、ある国や社会が、自らの過去――とりわけ植民地支配をめぐる歴史について、これまでどのように語ってきたのか、そして何を語ってこなかったのかに立ち返り、その不完全さを引き受けていく、ひとつのプロセスを指しています。ただ、この言葉に対応する概念は、フランス語には存在しません。「振付的に“Truth Telling”を行うとはどういうことになり得るのか」を考えるにあたって、適切な訳語を探すのに、かなりの時間が必要でした。
ここで突き当たるのは、言葉自体が存在しなければ、理解することも想像することも、さらには実践すること自体も難しくなってしまうという問題です。その中で、どうしたら責任を引き受けられるのか。アーティストたちが使う言い回しやローカルな言葉の中には、フランス語や英語には存在しない、ほぼ翻訳不可能な言葉がたくさんありました。それらは、ときに想像力の体系そのものを形作っています。
あるオーストラリア先住民の作家が指摘しているのですが、英語では円環的な時間を語るときに「non-linear time(非線形の時間)」と言いますよね。でも、そこではすでに「non=否定」から始まっている。別の時間概念を想像しようとした瞬間に、すでに否定を前提にしてしまっているんです。
言語は、私たちがどう語り、どう感じるかを形づくっています。だからこのプロジェクトは、別の思考、別の身体感覚の回路への招待でもありました。エコ・ソマティクスが示すように、身体と環境は切り離せない。先住民の思考に共通するように、私たちは決して宇宙のなかで孤立した存在ではなく、自分が立つ土地に対して責任を持ち、より大きなシステムの一部として生きている。それは、私たちが失ってしまった別の「責任」の体系です。この点でFORUMでは、とても基本的なことをあらためて確認していたのだと思います。

© Elyes Esserhane
■ 「共に感じる時間」が立ち上がったオープニング
筆者が現地で立ち会えたのは、5日間のうちわずか1日。それでもその体験は強烈だった。冒頭に置かれたオープニング・ギャザリングは、このFORUMが何を大切にし、どのような姿勢を立ち上げようとしているのかを、言葉以前に振る舞いによって示す時間となっていた。
5つの地域から集ったアーティストたちが、バトンリレーのように場をモデレートしていく。そこに、演者と観客、ホストとゲストを隔てる明確な境界線はない。円を描くように配置された座席——その内側に小さく親密な共有圏が立ち上がったかと思えば、今度はその外側を大胆に駆け回る身体が現れる。空間のあり方は固定されることなく、絶えず揺らぎ、書き換えられていった。
各組が持ち寄る実践は、言語や歴史、土地に深く根差した、極めてローカルな色彩を帯びている。けれどもそれらを共に体験していくうちに、単なる差異としてではなく、感覚のレベルで通じ合う何か——「分かち合う可能性」——が、ゆっくりと立ち上がってくるのを感じた。異なる実践の共存と共鳴。それぞれが地域を代表する役割を過度に背負わされることも、「マイノリティ」という枠に括られて過剰に分断され、孤立することもない。それでいて、安易に均質化されることもなく、ばらばらのまま何かを通じ合わせ、互いに作用し合うことで、緩やかな連帯が立ち上がっていたように感じられた。
— リヨンでは、どれくらいの時間を一緒に過ごしたのですか?
実際に一緒にいたのは、1週間ちょっとですね。ただ、このプロジェクトには、最初に思い描いていたけれど実現できなかった構想があります。それは、ノマド的なかたちで、アーティスト同士が互いの場所を訪れ、迎え合うというものです。「ホストする/迎える」という行為が、このプロジェクトの中心にあったからこそ、最初は、彼らがそれぞれの国や地域で互いをホストする姿を構想していました。
でも現実的には、距離も遠く、費用も時間もかかり、何よりそれをどう説明し、どう可視化するのかという点を助成機関や資金提供者に伝えるのがとても難しかった。アーティストが出会い、何かが生まれるかもしれない——でも、何が生まれるかは分からない。その不確実性を引き受けてもらうのは簡単ではありません。
結果として、事前のやり取りはオンラインになり、全員が同じ空間に集まったのは、ビエンナーレの会期が始まってからでした。でも驚いたのは、会場であるシテ・ド・ラ・ガストロノミーで実際に会った瞬間、すべてがとても速く動き始めたことです。すでに互いの提案や関心を知っていたからか、まるで前から知り合いだったかのように、ごく自然に、有機的かつ身体レベルの関係が立ち上がっていった。それは本当に美しい光景でした。
そして全員が集まってからわずか2日間で、アーティストたちはFORUMのオープニングをともにつくり上げました。正直に言えば、直前まで何が起こるのか、誰も分かっていなかったんです。分かっていたのは、「円」が必要だということだけで、会場が来場者全員を受け入れられるかどうかさえ、開始20分前まで定かでなかった。でも結果的に、あのオープニングは、このプロジェクトが照らし出そうとしていたものを、まさにそのまま体現するものとなりました。アーティスト同士の実践が互いに接続し、共鳴し合い、その流れ自体が観客を巻き込んでいった。説明や形式的な導入を必要とすることなく、すべてはそこにあった——それは、アーティストたちが「共に在る」時間をつくり、「共に感覚をひらく」状態を立ち上げていたからだと思います。フランスの哲学者ジャン=リュック・ナンシーが言う「être-en-commun(共存在)」という感覚にとても近いものでした。
完成品や成果を見せるのではなく。ただ、アーティストたちが日常的に実践している関係のあり方を、そのまま共有すること。だからこそ、結果が直前まで分からない、極めて予測不能なプロジェクトでもありました。こうした試みが実現したのは、ビエンナーレのチーム、とりわけ技術や広報のスタッフがこの予測不可能性を受け入れ、プレッシャーも緊張もかけることなく柔軟に支えてくれたからです。大規模で制度化されたフェスティバルの文脈では、こうしたプロジェクトは本当に稀ですし、運営やマネジメントのあり方そのものを問い直すことにもつながります。そして、その都度どのように開かれていくかを選択し続けたこのFORUMは、決して脆弱だったわけではありません。むしろとても強靭で、観客とアーティストと絶えず共創を続ける、きわめて特異なプロジェクトだったと思います。

© Elyes Esserhane
— 私は、あのオープニングのあり方に強く感銘を受けました。集団的な実践として始まったあの有機的な共有の場は、とても寛大であると同時に、既存の形式を揺さぶるラディカルさを持っていたように思います。もしクラシックなカンファレンスやキーノートから始まっていたら、観客として私は、どこか安全な距離のなかに留まり続けていたかもしれません。けれどもあのオープニングでは、「観客」と「アーティスト」という境界を越えて、「共に在ること」そのものが体験としてまず立ち上がりました。
オープニングに関しては、「ショックを与えたい」とか「挑発したい」という意図があったわけではありません。ただ、アーティストたちが同じ空間で共に過ごすなかから自然と生まれてきたのがあの形だったんです。もちろん、一人15分ずつ自分の実践を紹介するというクラシックな形もありえたと思います。でも、彼らはそれを選ばなかった。結果的に、自分たちが日常的に用いている方法——つまり円をつくり、知を共有する非階層的なあり方——を、そのままオープニングに持ち込みました。
私たちが「上演」や「パフォーマンス」として知っている形式は、実はとても植民地的で排他的な構造をもっています。舞台があり、観客が向かい合う。行為する者と鑑賞する者が明確に分かれ、権威をもった声が前に立って賞賛を受ける。こうした鑑賞のシステムは、ヨーロッパで形成され、やがて世界中に広がっていきました。でも、今回集まったアーティストたちは、そうした前提とはまったく異なる関係性のなかで日々実践を続けています。
もちろん、ヒエラルキーが全く存在しないわけではありません。特に知識の伝達と共有の場面においては。たとえば、オーストラリアのマルゲクや台湾のファンガス・ナヤウのコミュニティでは、長老や賢者が許可を与え、知を伝える役割を担っています。準備ができるまで、知ることも語ることもできない領域がある。文脈は違いますが、歌舞伎の世界で、年齢や経験が足りないと特定の役を演じられないということにも少し似ているかもしれません。
私が強く感じたのは、あのオープニングは「共に在る(être en commun)」だけでなく、身体のレベルで、さらには内臓のレベルで「共に感じる(sentir en commun)」時間だったということでした。
この形式は、人によっては戸惑いを生むものでもあります。ピッチやキーノートやディスカッションなら、おおよそ想定できるし、予定にも組み込みやすいですが、今回は誰にとってもその場で起こることに出会い、そこで見えてくるものを受け取っていくような時間でした。実際、「何をするのか」と何度も聞かれましたが、いつも「わからない、見てみないと」と答えるしかなかった。でも、疑問を持って問い続ける力を失いつつある今、この「分からなさ」こそが大切だったと私は思っています。
アメリカのトーマス・F・デフランツがワークショップで投げかけていた「What do you wonder about?」という問いも、その姿勢をよく表しています。「wonder」とは、答えをすぐに得ることではなく、考え続けること。立ち止まり、注意深く問いを転がし続けること。答えが今日出なくてもいいし、永遠に出ないかもしれない。それでも問いのそばに留まる態度です。同時にそこには、思考や身体が場のなかを少し「さまよう(wander)」ことを許す感覚も含まれていると思います。
キュレーターである私にとって印象的だったのは、このプロジェクトが「完成されたもの」として私たちの手の内にあるわけではなかったことです。冊子やウェブサイトは存在しても、そこで何が立ち上がるかは最後までわからない。プロジェクトはキュレーターやアーティストの所有物ではなく、ともに創造されたものであり、とても繊細でありながら、しっかりとした共在の感覚を持ち、予測不可能な強さを宿していました。(リヨンの国際美食館を会場としていたので)料理の比喩を借りるとすれば、まるでマヨネーズみたいなものかもしれません。レシピは完璧に思えても、全部の材料が揃っていても、実際混ぜてみないとうまく仕上がるかはわからない。そして今回それは、素晴らしくうまくまとまったんです。
▶︎ 【第3回に続く】
【連載】
共に在ること、共に感じること —— リヨン・ダンス・ビエンナーレ2025「FORUM」をめぐって
第1回
– フェスティバルにおける国際性とは —— ローカル性と普遍性
– 身体を通して世界を考えるために —— 「作品」だけではないダンスの在り方
第2回
– 関係性のキュレーション —— アーティスト間の関係、観客との関係
– 言語が映し出す、別の思考、想像力、身体感覚
– 「共に感じる時間」が立ち上がったオープニング
第3回
– ホスピタリティに含まれる寛大さと緊張
– 「何をコンテンポラリーダンスと呼んでいるのか?」
– 螺旋を描きながら問い続ける —— キュレーションの権力と責任
取材・執筆・翻訳:呉宮百合香
▶︎ English version available here:
Being together, sensing together: on FORUM at the Biennale de la danse de Lyon 2025


