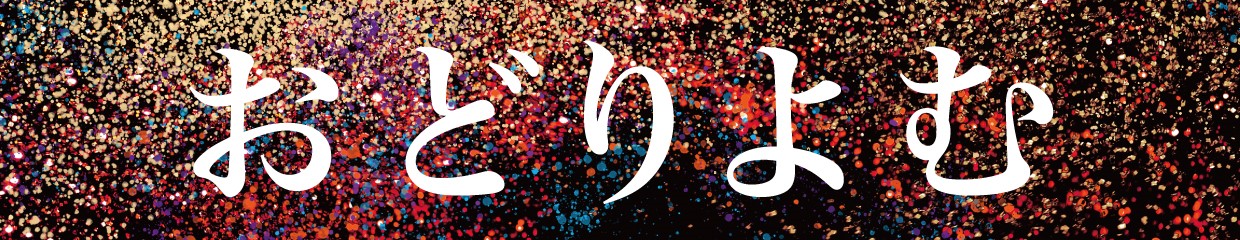振付をめぐるショートエッセイ①
動き/踊りのあるところ
#動き #踊り
私たちは、生きている限り「止まる」ことはありません。「動き」というのは空間上の移動だけでなく、身体の生命維持に必要な条件です。たとえ寝たきりになって移動できなくなろうとも、呼吸が続く限り、私たちの体は意識的にも無意識的にも動き続けます。呼吸に伴う胸部の収縮、瞼の開閉、皮膚のほんのわずかな引き攣り、重力と関係をとって姿勢を維持する機能など、たとえどんなに小さい動きであっても、それは「動き」そのものです。つまり、わかりやすいムーブメントなどがなく、一見動いていないように見えても、そこに人が(というか動物が)生きて存在している限りは、何かしらの動きがあるということになります。
舞踏家の大野一雄は、103歳で他界するまでずっと踊り続けたと言われています。足で移動できなくなると手を使っていざりながら踊り、それもできなくなりベッドに寝たきりになっても、音楽が聴こえてくればわずかに手を動かして踊りました。そして手が動かなくなっても、音が満ちたその空間で、大野は呼吸しながら踊っていました。呼吸の変化に伴うささやかな体の動き、わずかな表情の移ろい、その全てが、微細な、けれども崇高な踊りであったように感じられます。
翻って考えてみると、何を「踊り」とみなすかは、むしろ見ている人の気の持ちようによるところが大きいのかもしれません。もしかしたら大野は、本当は踊っていなかったのかもしれません(もちろん、踊っていたかもしれません)。動物や鳥を見て踊っているように感じたとしても、彼らに「踊り」という概念があるかどうかはわかりません。ましてや風で「舞う」木の葉は、意図を持って「舞っている」わけではないでしょう。ある動きを「踊り」と捉えるかどうかは、もしかしたら見ている私たちのマインドに依っているのかもしれません。究極的には、目の前に何もなくても、そこに「踊り」が出現することもあり得るのではないでしょうか。
▶︎「動き/踊りのあるところ」(宮川麻理子) #動き #踊り
・「その足先を伸ばす前に」(宮川麻理子) #身体 #テクニック
・「上演における振付的関係 —— 観客の経験という契機」(宮下寛司) #観客 #関係性
・「“Choreographies for you” —— 美術館における振付」(宮下寛司) #美術館 #空間
・「振付のフィールドとその概念の広がり、生態学的な振付へ」(吉田駿太朗) #劇場外 #自然
・「AIとダンスの融合 —— 振付の創造性」(吉田駿太朗) #AI #テクノロジー