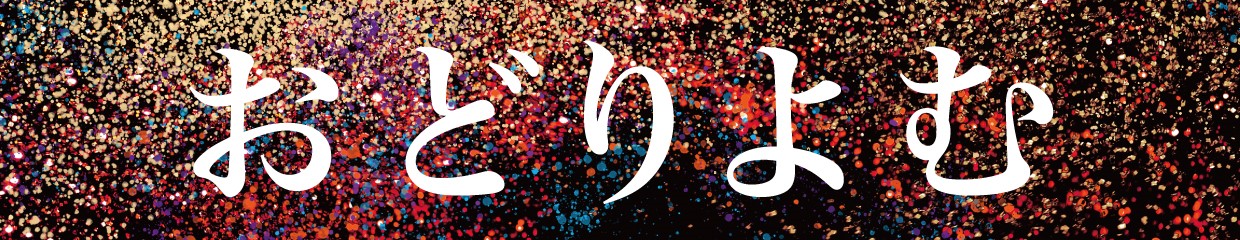振付をめぐるショートエッセイ②
その足先を伸ばす前に
#身体 #テクニック
数年前のことになりますが、若手のアーティストによるコンテンポラリーダンス作品を何本か見ていて、気になったことがありました。それは、ポーズした際や回転する際、ほとんど無意識的に足先をピンと伸ばしていたダンサーが多かったことです。おそらくモダンダンスやバレエを通して習得したテクニックのくせが、何気ない瞬間に現れてきたのでしょう。こうしたくせだけでなく、「これが正解」とされている動きをする/してしまう背景には、それまでに経験してきたダンスのテクニックやセオリー、ジャンルごとの美意識が多分に影響していると思います。もちろん、それが効果を発揮することもありますが、作品を創作する際に一旦立ち止まって、「これは、必要なのか」「なんで私はこれを美しいと感じるのか」と問い直してみてもいいのではないでしょうか。
一方で、習得したテクニック、その人の身体に蓄積されたダンスの記憶にフォーカスして、優れた作品を生み出しているアーティストも数多くいます。最近では、かつてバレエを習っていた(今はやめた)経験者を募集し、構成した倉田翠の作品『指揮者が出てきたら拍手をしてください』、日本舞踊の経験を作品に昇華した中川絢音(中川は今年のYDCにラインナップされています)、そのほかダンサーの経験・経歴そのものを作品化したジェローム・ベル Jérôme Belの一連の作品群(« Véronique Doisneau » « Cédric Andrieux » など)も思い浮かびます。
一度体が覚えたテクニックを捨て去ることは容易ではありませんし、完全に忘れる必要もありません。ただ少し意識的に、ダンス作品とテクニックの距離を改めて考えてみることで、新たな光景が見えてくることもあるのではないでしょうか。
・「動き/踊りのあるところ」(宮川麻理子) #動き #踊り
▶︎「その足先を伸ばす前に」(宮川麻理子) #身体 #テクニック
・「上演における振付的関係 —— 観客の経験という契機」(宮下寛司) #観客 #関係性
・「“Choreographies for you” —— 美術館における振付」(宮下寛司) #美術館 #空間
・「振付のフィールドとその概念の広がり、生態学的な振付へ」(吉田駿太朗) #劇場外 #自然
・「AIとダンスの融合 —— 振付の創造性」(吉田駿太朗) #AI #テクノロジー