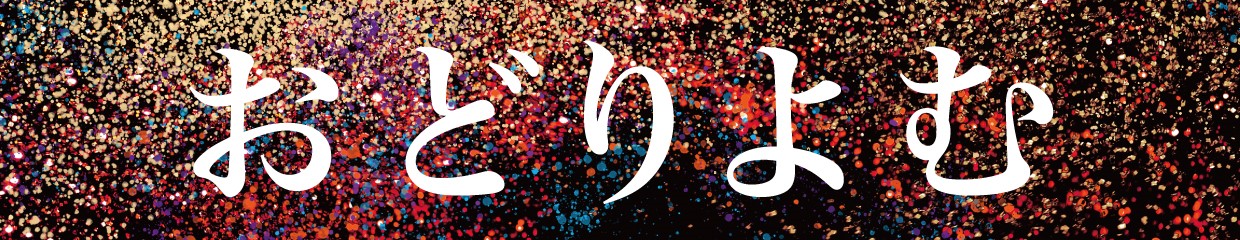振付をめぐるショートエッセイ⑤
振付のフィールドとその概念の広がり、生態学的な振付へ
#劇場外 #自然
質問:振付の教科書で、振付を最も的確に表す表紙のデザインは、どのようなものでしょうか。
—— 回答:上空から眺める舞台の平面図、そこに記された□が最適ではないでしょうか。*
西洋における振付(choreography)は舞台の平面図にある空白の□にダンサーの動作(ステップなど)を記し固定する概念でした。今や、その振付を表現するのはダンサーに限らず、音響、照明、映像など対象は広がり続けています。
では、振付のフィールドが劇場外へと移る際、振付概念はどう変化するのでしょうか。例えば、振付家アマンダ・ピニャは公共の場や山歩きでのパフォーマンスを提示します。参加者は土着的なコスモロジーからなる実践を通して、場所と身体の関係を位置づけ直し、感覚を再編成しながら、自然と「共にあること」の振付に向き合うこととなります。劇場版の『Climatic Dances / Danzas Climáticas』では、鉱害による人々と自然への被害とその感情の動き、山の変化への同調、そして民俗舞踊による儀式的な世界の再構成へと、複数の振付を繋いでいきます。つまり、フィールドが拡張する度に、多種の振付が複雑に絡み合い、撹乱し合う振付概念が導き出されるのです。
ピニャなら最初の問いにこう答えるかもしれません。
舞台は地球全体で、□は、幾重にも重なる大小の円だと。
それは地球環境や人間を含む生物、物質にまで想像力を働かせ、重奏する多元的感覚に橋渡しながら、振付けるという意志の現れでもあります。
* The dispute over movement and the non-time of the struggle. (Notes for a performance on the way (André Lepecki)の質疑応答からの抜粋
・「動き/踊りのあるところ」(宮川麻理子) #動き #踊り
・「その足先を伸ばす前に」(宮川麻理子) #身体 #テクニック
・「上演における振付的関係 —— 観客の経験という契機」(宮下寛司) #観客 #関係性
・「“Choreographies for you” —— 美術館における振付」(宮下寛司) #美術館 #空間
▶︎「振付のフィールドとその概念の広がり、生態学的な振付へ」(吉田駿太朗) #劇場外 #自然
・「AIとダンスの融合 —— 振付の創造性」(吉田駿太朗) #AI #テクノロジー